AtomicMods.com 売出し中

びっくりしました。
AtomicMods.comが売りに出されてます。事業自体を売却するみたいです。
何があったのかはわかりません。
そこのあなた、買ってみませんか?
最終更新: 2014/08/31(Sun)17:11
自作と修理を愛するブログ。トイラジ、電子工作、ボルティー、NucleusCMS 、いろいろゴソゴソやってます3Dプリンター / 3Dスキャナーも -kyu-
Home > XMODS

びっくりしました。
AtomicMods.comが売りに出されてます。事業自体を売却するみたいです。
何があったのかはわかりません。
そこのあなた、買ってみませんか?
バッテリー交換でその弱さを露呈したラジカンタイヤ。手持ちの部品には良いものは残っていないことは明白なので、ちょっとした口実をつくって家族ともども近所のラオックスへ行ってみました。なぜ家電量販店? それはアソビットが併設されているからです。
アソビットは実は苦手です。ちょっとばかり「濃い」お客さんが多いので。今回も、Nゲージの前でじっと考え込んでいる方やなんかのフィギュアを手に取るカップルなんかが散見されました。まあ、自分もヒトのことは言えませんが(笑)
この店舗はミニ四駆系のパーツストックが豊富です。ミニ四駆PROの実物を初めてみました。噂の両軸モーターやらなんやらと同じ棚に、ありましたタイヤ。ぱっとみでこのあたりかなぁと思われるタイヤを手に取りレジへ行こうとしたとき、なにやら見慣れないパッケージのタイヤが。バクシードです。
バクシードというのは、早い話がバンダイ製のミニ四駆ですな(失礼)。てっきり「爆シード」だと思っていたのですが、正式には「バクシード」というらしいです。バンダイ以外にもアオシマ、ミツワ、ウェーブ、GSIクレオス、京商から製品が出ているというのは意外でした。京商のシャーシはミニッツのボディが載せられるらしいです。
模型メーカー数社共同というと、1/700の艦船模型「ウォーターライン」シリーズが思い出されます。その昔少々凝ったことがありますが、タミヤ製が一番できが良かったです。バクシードもやはりバンダイ製が良いのでしょうかね。
話がそれてしまいました。入手したのはこのバクシード用タイヤでエンケイホイールとダンロップのディレッツァスポーツZ1のセット(SP-019)です。定価315円なり。

このダンロップタイヤ、XMODSのホイールにどんぴしゃでした。もちろんXMODSホイールのセンターのリブは削り落として、です。ハイトは低め。それらしいパターンの刻まれたトレッドもホイールと同幅。回転方向の指定があり、驚いたことに実物同様タイヤ側面にモールディングされています。かっこいいです。
コンパウンドはかなり軟らかめ。畳の部屋で試走したところ埃をかなり吸着してしまいました。いつものコースでもグリップは強烈でしょう。すぐ減ってしまいそうですが。
Mini-Z AWDの登場によりEVOも今ひとつ盛り上がらないXMODSですが、まだまだ続けますよ。…って、ラジカンの時も同じようなことを書いた記憶がありますなぁ(笑)
クルマの右側面から見たフロントナックルを模式図にしてみました。
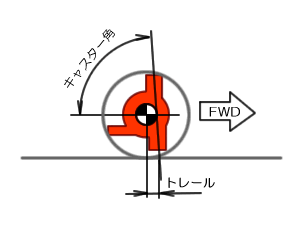
まずは一般論から。ご存知のとおり、キャスター角は路面に対するキングピンの角度、トレールはアクスル軸とキングピンの離れている距離のことを指します。ともに直進安定性の向上に貢献するようです。XMODSの場合はフロントサスペンションの構造が特殊なためキングピンという概念自体が一般的なRCと異なります。サスはキングピンの軸方向にはストロークしません。
キャスター角とトレールは数値で押さえたいところですが、なかなか測る手段が見つからずにいます。ラジカンやカスタマックスとは一線を画する部分であることは間違いないでしょう。まあ、あれだけガタのあるクルマでは、実際のところの効果は不明ですが(苦笑)。
これまた有名な話ですがノーマルの最小旋回半径はとても大きいです。本国並みの広い家ならともかく、一般的な日本の居間では何度も切り返しを強いられます。そこで考案されたXMODSの定番の改造のひとつに「舵角改善」というものがあります。タイロッドを曲げる機械的な手法と、ポテメに抵抗をかまして制御回路を騙す電気的な手法が有名。どちらもよりステアが切れるようになるというものです。我がランチア【XMODS】ストラトスには電気的な改造を施してあります。
さて、ステアを切るとナックル内部のドッグボーン先端の位置はどうなるでしょう。ドッグボーンは当然アクスル軸と同軸ですから、トレールがある分ドッグボーンも左右に動くことになります。ステアを右に切れば、右のドッグボーンは内側へ、左は外側へ移動します。
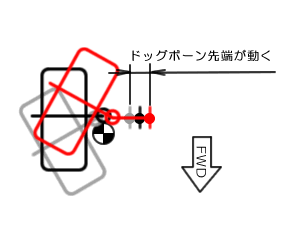
ドッグボーンはデフカップジョイントにかみ合っていて、少々ならカップの溝で軸方向の位置の変化を吸収できる構造ですが、舵角改善改造を行うと、その許容値以上にドッグボーンが移動してしまうようです。その結果、デフカップジョイントはデフギヤ側へ押し付けられることになります。
デフカップジョイントはラジアル荷重をベアリングで受ける構造です。フルステア時、デフカップジョイントは内側に入ろうとしますがベアリングユニットで規制されます。軸方向に荷重がかかるため、ベアリングの回転が渋くなります。
根本的な改善方法は、前輪の駆動系を全体的にクルマの左側へオフセットすることでしょう。ほんの0.5ミリ程度でよいのですがしかしそれはとても難しいことです。とすると、右のデフカップジョイントのミゾを深くするか、ドッグボーン先端を強度的問題が無い程度に短くするかしかないです。
ひたすらカップを削った結果が、以前記事にしたカップの破断でした。アルミ素材で作り直す羽目に陥ってしまいました。その後盛り削りで微調整を繰り返していますが、いまだ良い結果は出ていません。
滑りやすい路面でどのような挙動になるかというと、右にフルステアすると右前輪がロックしたような感じになり、右前輪の接地面を軸にくるりとスピンする感じです。特にカチカチのグリップしないタイヤを履いているとなおさらです。
オーナー(わたし)は忙しい忙しいと言っているにもかかわらず、毎日昼休みのお供として酷使され続けてきたわがXMODSストラトス、やっとフルメンテすることができました。電池交換以外でボディを外すのは実にひと月ぶりになります。
ちなみにアルミパイプを切った貼ったして製作したユニバーサルカップですが、その後二度ほど作り直して今にいたっています。最初のものはDカットしたシャフト部分が短すぎてベベルの穴を傷めてしまったのでボツ、二度目はカップ部分に差し込んだシャフトが浅すぎて、ドッグボーン勘合用の溝のところから破断してしまいました。三度目のものはどうやらうまく動いています。分解するのはこのユニバーサルカップをつけて以来ということですね。
フルメンテといっても特に難しいことをするわけでもなく、完全にバラしてひたすら掃除です。開けてみて驚いたのがタイヤの削りカスと堆積したホコリ。タイヤのカスは妙に粘っこくて、軽く拭いただけではとても落ちませんでした。
ベアリングはすべて外しZippoオイル漬けにしてシェイクシェイク。Zippo製洗浄オイルはすぐに真っ黒になってしまいました。
組み立て時は各部に注油。揮発性の高いオイルは流れ出してしまうので油膜を形成できず役不足ですが、手軽さからついついスプレーしてしまいます。ちなみになぜかCRC556ではなくWD-40を愛用しています。100円ショップ製シリコンオイルはべたべたしていまいちでした。
バラし始めてから組み立て完了するまで2時間半もの時間を要してしまいました。それだけ汚れがひどかったということです。
作業の前後で明らかに駆動系の音が変わりました。ギャンギャンうるさかったのがウソのように静かに。例えるならシュルシュルといったところでしょうか。
機械モノのコンディション管理にはメンテナンスが重要なのだなぁとあらためて思うのでありました。
アメリカの現地スタッフがXMODSを走らせていたという話を以前しましたが、その当人が研修のため来日しました。晩飯に誘われたので普段はあまり乗らない電車で小一時間かけて出動。彼の名前はデビッド、ボストン在住のベジタリアンです。
聞けばボストンオフィスのすぐ近くにRadioShackがあり、ほかに3人ほどでオフィス内特設サーキットで楽しんでいるとのこと。うらやましい。
同好の士なので話は早く、FETは換えたほうがいい、AWDは必須だなどと話に花が咲きました。
面白かったのはMini-Zの話。日本人は「ミニッツ」と発音しますが、アメリカでは「ミニジー」というそうです。確かに「Z」は「ゼット」ではなくて「ジー」。最初こちらの車種をきかれて「元はニッサンゼットスリーファイブオー」と説明したのがまったく通じなかったのもうなずけます。
オフィスのコースはパンチカーペットでタイヤはやはりMini-Z用を使っているらしいです。持参のPCに走行の様子を撮影した動画があって見せてもらいました。どちらかというとドリフトというよりグリップ走行主体。
モーターは何使ってると聞かれてTAMIYAのMINI4WDだよといったら納得してました。さすが世界のタミヤ。またドッグボーンはGPMのアルミアロイパーツが良いと薦められました。やっぱりドッグボーンっていうんですね。
今度アメリカへ来るときは是非XMODSをもってこいと念を押されて別れました。楽しいひと時でした。
サイト内検索
カテゴリ一覧
最近よく読まれている記事
最近のコメント
SKF: jzさん、初めまして。私も今さらなのですが、状況はjzさんよ... (2025/02/27)
SKF: 失礼しました。訂正します。 今でも教えて頂けるので → 今... (2025/02/27)
SKF: kyuさん、初めまして。もう古い話題なので今でも教えて頂ける... (2025/02/27)
jz: はじめまして。 今更ですが、202HWの制限解除のサポートはま... (2025/01/13)
kyu: はやとさんこんにちは。 わざわざご報告いただきありがとうご... (2023/07/14)
はやと: こちらのサイト等を見さして頂き、202HWの全画面化に成功し... (2023/07/14)
kyu: ひでぢさんこんばんは。 うまく行ったとのこと何よりです。 ... (2023/05/07)
ひでぢ: kyuさん いつもご教示頂きありがとうございます。 rootの取... (2023/05/07)
kyu: ひでぢさんこんばんは。 わたしもAndroidは詳しくないのです... (2023/05/06)
ひでぢ: kyuさん 何度もすみません、また間違えてましたね (正)sh... (2023/05/06)
ひでぢ: kyuさん すみません前にお送りした画面の内容でスペル間違い... (2023/05/06)
ひでぢ: kyuさん 引き続きのご相談になりますが、あれから以下①~③を... (2023/05/06)