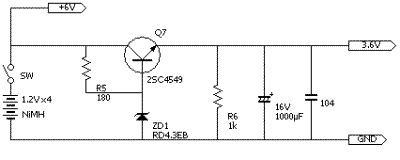モータドライバ
まずはここから。
ボランティアでおもちゃの修理をされている「おもちゃの病院」です。文章も平易で読みやすく、好感度大です。久しぶりに「人に伝えるための文章」の書き方というものを再認識しました。
こちらのサイトは特に電子電気関連の資料が充実しています。おそらく担当の方が電気畑のひとなのでしょう。
「リモコン・ラジコンなど動くおもちゃ」にモータドライブ回路例やTX-2/RX-2を使ったTAIYO-R/Cの回路図があります。このモータドライブ回路を参考にすることにしました。
リレーチューンと同様に、プラズマダッシュの定格4.2Aがドライブできることを目標に設定します。
トランジスタを選定するのに便利なのが東芝セミコンダクタのサイト。そしてこの道では有名なサイト 電子工作の実験室 のトランジスタ回路の基本設計法をもとにトランジスタ回路を設計しました。
ちなみに、HブリッヂならFETのほうが簡単だよという声が周囲から聞こえてきました。またはモータドライバ用の専用モジュールを使うとか。でも、電気シロウトには辛いのですよ。
できあがった回路図がこれです。
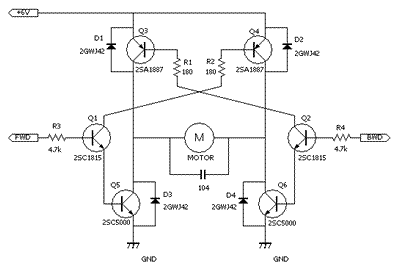
メインのトランジスタは2SA1887と2SC5000です。TAIYO零戦クラブで紹介されています。空モノはバックはしないのでドライブ回路は違いますが、定格10A以上で重量と大きさの両面から2SC5000がお勧めとのこと。2SA1887は2SC5000のコンプリメンタルです。これらのトランジスタにあわせて、ちょこちょこと計算しました。